「ヘルプマークを付けているメンヘラにも電車で席を譲るべきなの?」と疑問に思ったことはないでしょうか。
生活困難で周りの支援が必要な人がつけるヘルプマークですが、どんな人が対象で、どう接すればよいのかわからない人も多いはずです。
この記事では、ヘルプマークの基本知識から効果的な活用法まで詳しく解説します。また、最近話題の「逆ヘルプマーク」についても触れていきます。
この記事でわかること
- メンヘラに席を譲るべき?
- ヘルプマークとは?
- ヘルプマークの対象者
- ヘルプマークの入手方法
- ヘルプマークの活用方法
- 逆ヘルプマークとは?
正しい理解を深め、誰もが安心して過ごせる社会づくりに貢献していきましょう。
電車やバスでヘルプマークを付けてるメンヘラに席を譲るべき?

ヘルプマークを身に着けている人を見かけたら、メンヘラかどうかに関わらず、席を譲ることをおすすめします。外見からはわからない重病を抱える人もいるため、どうこう考えるよりもまず譲るべきです。
ヘルプマークは、援助を必要とする人を示す大切なサインです。ヘルプマークを付けている人の中には、精神的な病気や障害で日常生活すら困難な人もいます。
「メンヘラ」という言葉で一括りにされる場合もありますが、実際には深刻な症状と向き合っている場合も少なくありません。
うつ病やパニック障害、双極性障害などの精神疾患を患う方は、立っているだけでもつらいです。めまいや動悸、強い疲労感に襲われることもあります。
症状は外から見てもわからないため、周りに知ってもらいにくいのが現実です。しかし、ヘルプマークを付けることで「私は助けが必要です」というメッセージを発信できます。
ヘルプマークを見かけた時は、相手の気持ちに寄り添った声かけをしましょう。「もしよろしければ、お座りください」のように、優しい言葉で声をかけてください。
ヘルプマークとは?

ヘルプマークは、援助を必要とする人が、援助が必要であることを周りに知らせるためのマークです。東京都が2012年に導入し、現在では全国に普及している制度になります。
ヘルプマークは赤色のカードやタグ状になっていて、白いハートマークと十字のデザインが特徴的です。外見からはわからない障害や病気を抱える人が、周囲に支援を求める際に使用します。
最近では、電車やバス、公共施設などで見かけることが多くなりました。ヘルプマークを身に着けることで、電車で席を譲ってもらったり、緊急時に支援を受けやすくなったりします。
ヘルプマークの対象者はどんな人?

ヘルプマークの対象者は、外見からはわからない障害や病気で困っている人全般です。
身体の不自由さだけでなく、精神的な問題を抱える人も含まれます。精神的な症状により、長時間立っていることが難しい人や、人混みで不安を感じやすい人にとって、ヘルプマークは必須です。
具体的には、下記のような症状を持っている人は、ヘルプマークの対象になります。
- 内部障害(心臓病や腎臓病など)を患う人
- 精神疾患(うつ病やパニック障害など)を患う人
- 発達障害や知的障害を患う人
- 薬の副作用で体調が不安定な人
- 義足や人工関節を使用している人
- 妊娠初期の人
- 認知症の人
年齢や性別に関係なく、日常生活で困難を感じている方なら、誰でもヘルプマークの対象になります。
メンヘラはヘルプマークが必要?

精神的に重度のメンヘラには、ヘルプマークは必要といえます。ただし、症状の重さや生活への影響を考慮して、適切に判断しないといけません。
「メンヘラ」という言葉は精神的な不調を表すスラングですが、実際には深刻な症状で悩んでいる人も多いです。うつ状態やパニック発作などにより、日常生活に支障をきたす場合があります。
ヘルプマークを使用するかどうかは、メンヘラの症状や必要性によって判断しましょう。「電車で立っていることがつらい」「人混みでパニックになりやすい」などの症状がある場合は、ヘルプマークの利用を検討してください。
ただし、軽い気持ちで使用してはいけません。ヘルプマークは、本当に支援が必要な人のためにあります。医師や専門機関に相談しながら、ヘルプマークを使用するかどうか判断することをおすすめします。
ヘルプマークの入手方法
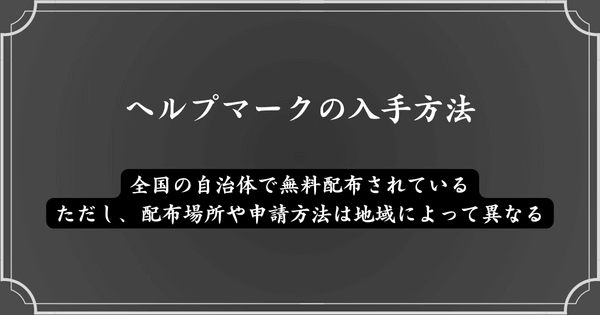
ヘルプマークは全国の自治体で無料配布されていて、簡単に手にいれることができます。配布場所や申請方法は地域によって異なるため、お住まいの自治体に確認してください。
ヘルプマークの配布場所は、主に各都道府県や市町村の福祉課が中心となっています。役所の障害福祉担当窓口で直接受け取ることが可能です。一部の地域では、保健所や福祉センターでも配布を行っています。
申請時には、簡単な申込書への記入が求められる場合があります。氏名や住所、困っている症状について記載するだけで、複雑な手続きは必要ありません。
即日交付される自治体も多く、当日中にヘルプマークを持ち帰ることができます。
外出が難しい人のために、郵送でヘルプマークを申請できる自治体も増えています。自治体のホームページから申込書をダウンロードし、必要事項を記入して郵送するだけです。
返信用封筒を同封すれば、数日から1週間程度でヘルプマークが届きます。電話での問い合わせにも対応している場合が多いため、不明な点があれば気軽に相談してみてください。
メンヘラも適切な手続きを踏めば、ヘルプマークを受け取れます。多くの場合、医師の診断書や障害者手帳は必要ありません。
もし日常生活で支援が必要だと感じるなら、遠慮なく申請してみましょう。
ヘルプマークを有効活用する方法
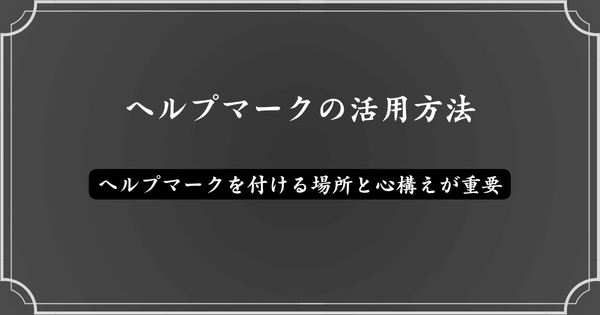
ヘルプマークを使用する場合、付ける場所と心構えが重要です。ヘルプマークを付けるだけでなく、必要に応じて支援を求める姿勢も大切になります。
メンヘラがヘルプマークを活用する際は、症状に合わせた使い方を心がけましょう。パニック発作や強い不安を感じやすい場面で、周りからサポートしてもらいやすくなります。
付けるべき正しい場所
ヘルプマークは目立つ場所に付けましょう。周りの人に気づいてもらえないと、ヘルプマークの意味がありません。
カバンの外側や洋服の胸元など、見えやすい位置がおすすめです。電車やバスに乗る際は特に、座席が必要であることを伝えるために、ヘルプマークを目立たせる必要があります。
ストラップタイプのヘルプマークなら、カバンの持ち手に取り付けると自然に目に付きます。カードタイプの場合は、定期入れと一緒にすることで、忘れることなく持ち歩きできるはずです。
持っておくべき心構え
必要な時は勇気を出して、具体的に支援をお願いすることも大切です。
ヘルプマークを付けていても、すべての人がヘルプマークの意味を理解しているわけではありません。「体調が悪いので、席を譲ってもらえますか?」など、声かけしないといけない場面もあるはずです。
メンヘラの場合、外見だけでは精神的な症状を理解してもらうのは難しい面もあります。しかし、ヘルプマークがあることで「何らかの困難を抱えている」ことは伝わりやすいです。
無理をせず、必要な状態であれば素直に周りのサポートを求めていきましょう。
緊急時の備え
ヘルプマークには、かかりつけ医の連絡先や服用中の薬の名前などを記載しておきましょう。緊急時の対処法も記載しておいたほうが良いです。
ヘルプマークには、緊急連絡先や服薬情報を記載できるシールが付いている場合があります。パニック発作や体調不良で意識を失った際、周りの人が適切な対応を取れるよう準備しておくことが重要です。
メンヘラにとっても、安心して外出できる環境づくりにつながります。
逆ヘルプマークとは?誰が作った?

逆ヘルプマークは公式に認められたマークではなく、ネット上で話題となった非公式のマークです。正式なヘルプマークとは異なり、自治体や公的機関が作成しているものではありません。
メンヘラと関連付けて語られることもありますが、明確な制作者は存在しないのが現状です。
逆ヘルプマークが生まれた背景
逆ヘルプマークの概念は、SNSや掲示板などのネット上で広まりました。一部の人々が「ヘルプマークを悪用する人がいる」という批判から、皮肉を込めて作られたとされています。
しかし、批判的な考え方は本来のヘルプマークの趣旨に反するものです。
正式なヘルプマークは、外見からはわからない生活困難な人への支援を促すために作られました。批判的な目的で生まれた逆ヘルプマークとは、根本的に異なります。
公式ヘルプマークとの違い
逆ヘルプマークは、どこの自治体でも配布されていない非公式のものです。
対して、正式なヘルプマークは東京都が開発し、現在では全国の自治体で配布されています。赤い背景に白いハートと十字のデザインが特徴的で、多くの人に認知されているマークです。
メンヘラも正式なヘルプマークの対象者に含まれます。逆ヘルプマークのような非公式なものではなく、適切な手続きを経て正式なマークを利用することが大切です。
【まとめ】ファッション感覚でヘルプマークを使わない
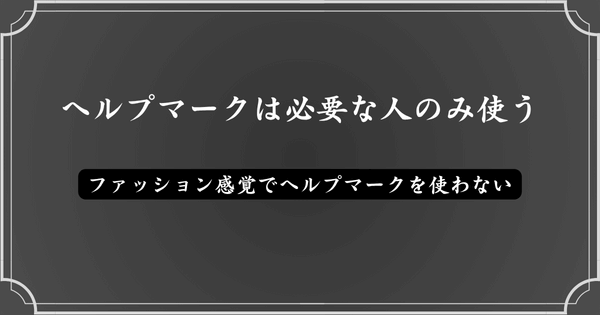
ヘルプマークは、外見からはわからないけど、生活が困難な人への支援を促す大切なものです。精神的な症状で悩む方も含め、多くの人が日常生活での支援を必要としています。
ヘルプマークを見かけた際は、相手の気持ちに寄り添った声かけを心がけることが大切です。断られても気を悪くせず、思いやりの気持ちを持って接することで、その人の心の支えになるかもしれません。
一方で、非公式の「逆ヘルプマーク」のような批判的な概念に惑わされることなく、正しい情報に基づいて判断することも重要です。困っている方への理解を深め、できる範囲でサポートしていく姿勢が求められています。
ヘルプマークを通じて、誰もが安心して生活できる優しい社会を作っていきましょう。小さな配慮や思いやりが、多くの人の日常を支える力になるのです。
